求職者を魅了する採用コミュニケーション術とは?【採用支援コラム Vol. 2】
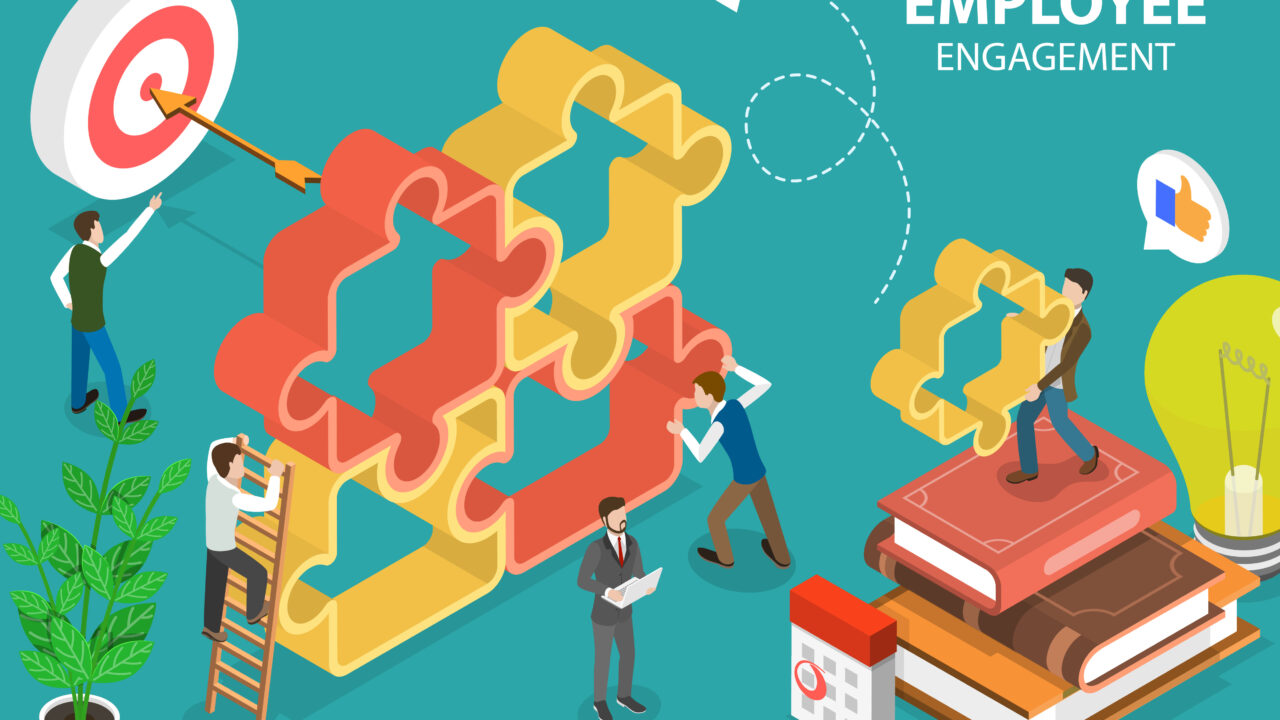
採用担当者の皆さんは、こんな課題を感じていないでしょうか。
「応募は集まるがミスマッチが多い」
「説明会の参加者が本選考につながらない」
「内定承諾率が上がらない」
こうした悩みは、決して一部の企業に限ったものではありません。
労働人口の減少、価値観の多様化、情報収集手段の変化――採用を取り巻く環境が大きく変わる中で、多くの企業が共通して直面している課題です。
そこでF&S CREATIONSでは、採用担当者が抱える課題に応えるために、「採用コミュニケーション術」をテーマとしたセミナー動画を制作しました。
この動画は単なるノウハウ紹介ではなく、採用現場のリアルな悩みに寄り添い、明日から実践できる改善のヒントをお届けすることを目的としています。
採用担当者がつまずきやすい採用コミュニケーションのポイント
「せっかく説明会や求人票を用意しても、求職者の心に響いていない」
――そんな状況を生んでしまう背景には、以下のような落とし穴があるかもしれません。
・求める人物像が曖昧
「いい人材が欲しい」といった抽象的な表現では、社内での定義が統一されず、結果として伝えるべきメッセージがぼやけてしまいます。
・求人情報が似たり寄ったり
「成長できる」「風通しが良い」など、よくある表現では競合との差別化が難しくなります。
・求職者の関心とズレている情報
仕事内容やキャリアの展望を知りたい求職者に対し、福利厚生や制度面ばかりを強調してしまうケースも見受けられます。
こうしたズレが積み重なると、応募数の低下や早期離職といった問題が表面化し、採用の質と効率が大きく揺らいでしまうことになりかねません。
惹きつける採用コミュニケーションの3原則
動画では、求職者の心を動かすためのポイントを、以下の3つに整理しています。
①欲しい人材を言語化する
採用要件が曖昧なままでは、訴求ポイントも曖昧になります。
まずはターゲット人材を具体的に言語化することが第一歩です。
②万人受けではなく、ターゲット人材に響くメッセージをつくる
「誰にでも響く」メッセージは、裏を返せば「誰の心にも強くは響かない」ということ。
特に欲しい人材にフォーカスし、その人が「ここで働きたい」と思える言葉を選ぶことが重要です。
③求職者が本当に知りたい情報を伝える
会社が伝えたいことと、求職者が知りたいことはしばしば異なります。
求職者視点に立ち、選考のフェーズに応じて適切な情報を届けることが欠かせません。
この3つのポイントを押さえることで、採用活動は単なる情報発信から“共感を生む採用”へと進化します。
採用コミュニケーション術についてプロの採用コンサルタントが解説
本動画で講師を務めるのは、リクルート出身で合同会社KAKERUの採用戦略ディレクターとして活躍する百合本拓也氏と、JTBグループ出身で経営コンサルティングの実績を持つ伊藤豪規氏。
これまで数多くの企業の採用課題に向き合ってきた両氏が、豊富な知見をもとに、採用コミュニケーションのポイントをわかりやすく解説しています。
採用コミュニケーションを見直すきっかけに
採用活動は、単に「情報を伝える」だけでは不十分です。
求職者の心を動かし、「ここで働きたい」と思ってもらうためには、惹きつけるためのコミュニケーション設計が大切です。
この動画は、悩める採用担当者に「採用コミュニケーションを本質から見直す」きっかけを提供するものです。
現在の採用活動に課題を感じている方は、ぜひ一度視聴してみてください。
新しい気づきや改善のヒントが、きっと見つかるはずです。